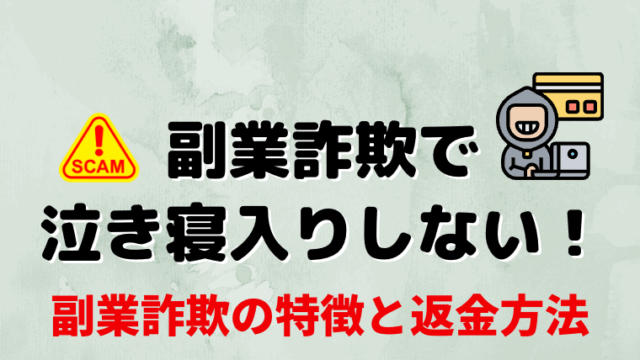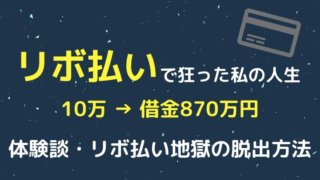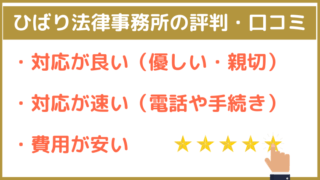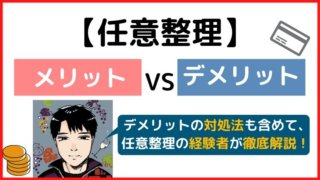スマホの普及やインターネットの利用層拡大にともない、ネット詐欺の被害が増加しています。
ネット詐欺に合わないためには、基礎知識と対処方法を知ることが大切です。
本記事では、ネット詐欺の種類やよくある事例、対策方法についてくわしく解説します。
この記事を読んでわかること
- ネット詐欺の概要と種類
- ネット詐欺のよくある事例
- ネット詐欺の被害に遭った人の口コミ
- ネット詐欺に遭わないための注意点
- ネット詐欺に遭ってしまったときの対処法
ネット詐欺の相談におすすめの事務所
実績が豊富で対応スピードも早い事務所です。LINEで気軽に相談可能。
着手金0円・相談料0円・調査料0円です。
こちらも詐欺問題に力を入れている司法書士事務所です。
費用の分割相談も可能。
目次
ネット詐欺とは?

ネット詐欺とは、インターネットを利用した詐欺行為のこと。
▼よくあるネット詐欺の例
- 偽のショッピングサイトから商品を注文しても商品が届かない
- 偽のサイトでIDやパスワードを入力したら個人情報が盗まれた
- 偽の電子メールで「振り込み手続きが必要です」と言われ、高額の手数料を支払ってしまった
このように、金銭を騙し取られたり、個人情報が抜き取られたりといった被害が生じます。
これらの手法は常に進化し、巧妙な手口が多いため、正しい情報や知識を身につけたうえで対策をすることが重要です。
▼ネット詐欺についてのニュース記事はこちら
「最新のディズニー体験をお届けします」などとメールを送り、本文にあるリンクを開くと詐欺サイトにつながり、個人情報やカード情報を入力するように促され抜き取られる詐欺が発生。
参照:ディズニーかたるフィッシング詐欺が発生中 最新情報メールと見せかけカード情報狙う
「ウイルスに感染」との警告画面が表示され、個人情報を入力したところ、遠隔操作ソフトがダウンロードされ49万円を騙し取られた詐欺。同様の被害で250万円送金してしまった被害も。
参照:「サポート詐欺」で49万円詐取、遠隔操作で手数料振り込み中に“ゼロを足す”斬新な手口
「地震被災者のために寄付をしよう」などと呼び掛け偽募金サイトへ誘導し、支援金を騙しとる詐欺が発生。
ネット詐欺の種類

ネット詐欺の被害を防ぐには、ネット詐欺の手口に合わせた対策が必要です。
▼ネット詐欺の主な種類
- フィッシング詐欺
- ワンクリック詐欺
- 架空請求
- SNSアカウント乗っ取り
- 偽警告
- 偽ECサイト
- ランサムウェア
具体的にどのような手口によって被害が発生しているのか、ひとつずつ確認していきましょう。
フィッシング詐欺
フィッシング詐欺とは、偽のウェブサイトや電子メールを使って個人情報やパスワード、クレジットカード番号などを騙し取る手口です。
銀行やショッピングサイトなど、実在する企業や金融機関のサイトになりすましたり、電子メールで偽のリンクを送信したりして、個人情報を入力させる手法が代表的。
ワンクリック詐欺
ワンクリック詐欺は、Webサイトやアプリなどで、ユーザーがボタンを1回クリックするだけで高額な課金がされる手口。
具体的には、偽装された成人向けサイトの動画の再生ボタンや、アプリのインストールボタンなどをクリックして起きる被害が確認されています。
サイトの閲覧や動画を視聴しただけで、「料金の支払いをしなければ法的手続きを執行する」という旨のメッセージが表示されて、実際に料金を支払ってしまったケースが多くみられます。
架空請求
架空請求とは、ある日突然身に覚えのない請求書やメールが送りつけられ、料金を支払わせる詐欺の手口です。
たとえば、「注文したわけでもないのに商品が配達され、支払いを要求される」「架空のサービスを提供しているとして、覚えのない請求書を送りつけられる」などの被害が確認されています。
SNSアカウント乗っ取り
TwitterやInstagramといったSNSアカウントを乗っ取り、詐欺行為を行う手口です。
特に怖いのが、「乗っ取られていることに気づかず、スパムメールを拡散してしまった」など、自分だけでなく周囲のアカウントにまで被害を拡散させる恐れがあること。
偽警告
偽警告とは、Webサイトにアクセスすると「ウイルスが検出されました」「今すぐセキュリティソフトをダウンロードしてください」などの偽警告画面を表示して料金を請求する手口です。
偽警告により、クレジットカード情報や個人情報まで抜き取られてしまう被害が生じます。
偽ECサイト
偽ECサイトとは、相場より大幅に安い商品やサービスを扱う偽ECサイトで商品を購入させ、代金を騙しとる手口です。
代金を支払ったにもかかわらず、商品が送られないケースや粗悪品・偽ブランド品が配達されるケースがあります。
また、人気商品を扱う大手ECサイトに偽装されたものも多く、本物を見分けるのが以前よりも難しくなっています。
ランサムウェア
ランサムウェアとは、PCやスマホをロックして使えない状態にしたうえ、ロック解除のための代金を要求する手口です。
いきなり動かない状況となり、焦って代金を支払ったものの、ロックが解除される保証はなく、泣き寝入りになるケースが相次いでいます。
\相談も調査も無料/
ネット詐欺のよくある事例
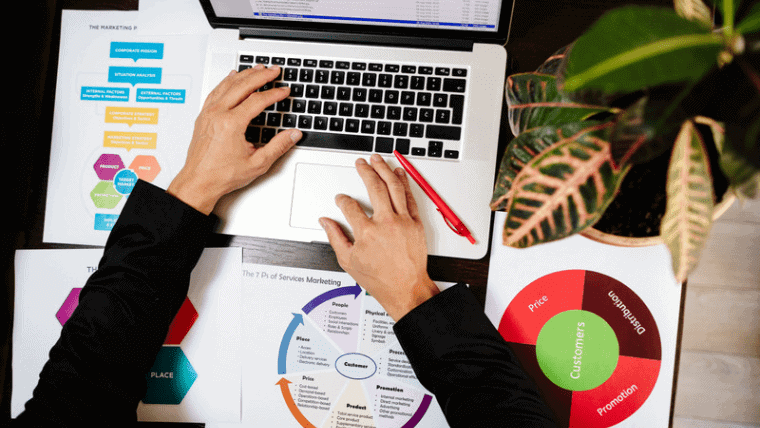
ここでは、ネット詐欺のよくある事例について解説します。
以下の事例に当てはまる場合は、注意してください。
支払い画面が表示されたが無視して大丈夫?
有料サイトのコンテンツ内容を確認しようと画面をダブルクリックしたところ、会員登録され、高額な料金を請求する支払い画面が表示された。
クリックしただけであれば、相手側は氏名や住所、電話番号といった個人情報まではわかりません。
支払い画面が表示されても、個人情報の入力はせず相手にしないようにしましょう。
「民事裁判で少額訴訟手続きを行う」と手紙が届いた
有料サイトの閲覧履歴があるとして、「民事裁判で少額訴訟手続きを行う」旨の手紙が届いた。
少額訴訟手続きの通知は裁判所から届きます。
「特別送達」で送られるので、以下を確認してみましょう。
- 「特別送達」と記載された封書かどうか(はがきや普通郵便では届きません)
- 郵便配達員から手渡しされ「郵便送達報告書」に署名または捺印を求められたか
- 支払督促や少額訴訟の呼出状の「事件番号」「事件名」が記載されているか
裁判所からの通知ではない場合、無視して問題ありません。
しかし、不安であれば弁護士に相談してみることをおすすめします。
なお、本物か否かの確認がとれるまでは、封書に記載された連絡先には連絡をしてはいけません。
請求内容を確認しようと安易に連絡をしてしまうと、電話番号や個人情報を提供してしまうことになりかねないので注意が必要です。
架空請求に対してお金を振り込んでしまった
架空請求だと思わずに、実際にお金を振り込んでしまった…取り返すことはできないのか。
すでにお金を振り込んでしまった場合、返金請求や訴訟を起こそうとしても相手がわからず、泣き寝入りになることも多いようです。
しかし、弁護士に相談してみると解決するケースもあるので、まずは相談してみましょう。
ネット詐欺の被害に遭ってしまった人の口コミ

ここでは、実際にネット詐欺の被害に遭ってしまった人の口コミを紹介します。
5月に被害にあったFCRキャブレターのネット詐欺
被害回復分配支払申請書なる書面が届いた。
相手方の口座が凍結されて、分配金申請書を提出した被害者の被害額から割合を出して、相手口座の残金にそれぞれの割合を計算した額が返金されるみたい。
口座の残金は14万6千円程、、、いくら返金あるかな pic.twitter.com/JVFRMUSI2J
— ✨玉子✨ (@AJfVcatCY7myXCh) November 16, 2022
ネット詐欺の返金額は、相手口座の残金で計算されるとのこと…早めの対応が大切ですね。
どなたかお知恵を。。
多分ネット詐欺に被害にあいました。
ホームページ大きいので安心してしまったのですが、キャンペーンで振込のみとのことで郵便局に振込
その後届かないので連絡したところ返事もなし、ホームページの電話もFAXも現在使われておりません😢
警察の窓口混んでて通話できず
— chikako❣️シンママのキレイと元気を応援✨ (@ckkmrt) May 19, 2022
悪徳業者と連絡がつかないうえに、警察の窓口が混んでいて通話ができない状況とは心配になりますね。
ネット詐欺に引っ掛かり、被害届を提出しに警察署に。刑事さんの素晴らしい段取りで40分ほどで終了。調書も完璧で感動。
18年前にもネット詐欺に遭い、武蔵野警察署に被害届を出した。2時間程刑事からの説教(なんでネットなんかで買うんだ?)があり、調書も最低で事件解決せず、被害届出し損でした。 pic.twitter.com/j5qTM4HdRy
— きのした (@tokyospitz) December 18, 2022
警察は、必ずしもネット詐欺の解決に向けて動いてくれるとは限りません。
また、被害届を出しても解決につながらないことが多いです。
ネット詐欺被害に遭って通報したけど警察は何もやってくれなかった
>例えば通報してきた詐欺事案なんかほとんどやってくれないよ。
— 土偶 (@dogu_fm) February 7, 2021
こちらも「警察が何もやってくれなかった」との口コミです。
賀来賢人 ネット詐欺被害を語る 1ヵ月前の注文品未だ届かず 「甘く見ないで」https://t.co/mf13wDqaRC
— mazun (@mazun87041592) April 2, 2021
芸能人でもネット詐欺被害に遭う時代のようですね。
ネット詐欺の被害に遭わないための注意点

ネット詐欺の被害に遭わないために気をつけることは、以下の4つです。
- ネット詐欺の手口を把握しておく
- あやしいメールやSMS、SNS、URLは開かない
- 詐欺サイトにアクセスしてしまっても無視する
- OSやアプリ、セキュリティソフトを最新にしておく
ネット詐欺の手口を把握しておく
本記事で紹介したようなネット詐欺の種類や手口を把握しておくことで、被害に遭う可能性を低くすることができます。
ネットの情報もチェックして、常に気をつけておきましょう。
SNSで調べてみると、同じ手口で詐欺に遭った人の情報が出てくることもあります。
あやしいメールやSMS、SNS、URLは開かない
あやしいメールやSMS、SNS、URLが届いたときは、すぐに開いてはいけません。
本物そっくりで見分けがつかない場合でも、届いたURLからは開かずに、公式サイトにアクセスする習慣をつけるなど、対応を工夫することが大切です。
詐欺サイトにアクセスしてしまっても無視する
料金の請求画面が表示されたり、身に覚えのない請求書が届いたりしても、焦らずに無視しましょう。
記載されている連絡先に電話したり、表示にしたがって代金を支払ったりすると、二次被害に遭う可能性が高まります。
アクセスしてしまったとしても、個人情報やカード情報を入力していなければ、被害リスクは低いので、極力関わらないようにしましょう。
OSやアプリ、セキュリティソフトを最新にしておく
ネット詐欺は、OSやアプリなどの脆弱性を狙って攻撃されることで、被害につながる可能性があります。
アップデートを怠らず、常に最新の状態を維持するようにしましょう。
ネット詐欺に遭ってしまった場合の対処法

ネット詐欺に遭ってしまったら…泣き寝入りせず、まずは相談できるところを探しましょう。
ここでは、ネット詐欺に遭った際の対処法をまとめます。
まずは早めに弁護士・司法書士に相談!
相談しやすく、解決までの期間が早いのは、弁護士・司法書士事務所です。
ネットで調べると、警察や国民生活センターの情報も多くみられますが、どちらも適切に対処してくれるまで時間がかかります。
警察・国民生活センターに相談するケースについては、以下で解説します。
詐欺被害に遭ってしまったら、一刻も早く弁護士や司法書士に相談しましょう。
\相談も調査も無料/
警察に相談するケースとは
「あまりにも悪質で、悪徳業者を懲らしめたい!」そう思った場合には、警察に相談するのもひとつの方法です。
警察に相談した場合、ネット詐欺に関して被害届を出す方法と告訴状を出す方法の2種類となります。
しかし、被害届を出しても、実際に捜査してもらえるとは限りません。
告訴するには、告訴状の作成を弁護士に依頼しなければならないケースもあります。
警察に相談して長時間頭を悩ませるよりも、弁護士や司法書士に相談した方が早期解決につながるでしょう。
国民生活センターに相談するケースとは
国民生活センターへ相談すると、「悪質だ」と判断されれば業者に対して調査が入ります。
しかし調査が入るものの、国民生活センターはあくまで業者の取締りがメイン業務となるため、返金請求は受け入れられません。
悪質業者に対して、「即座に返金請求をおこないたい」という場合は、弁護士や司法書士に相談する方が、迅速かつ確実な方法と言えるでしょう。
ネット詐欺に遭ったら弁護士・司法書士に相談しよう

本記事では、ネット詐欺の特徴や対処方法をまとめました。
ネット詐欺に遭ったと思われる場合、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士に相談すれば、泣き寝入りせずに返金できるケースもあります。
時間が経つほどに対応が難しくなりますので「あやしい…」と感じた時点で、早めに相談しましょう。
ネット詐欺の相談におすすめの事務所
実績が豊富で対応スピードも早い事務所です。LINEで気軽に相談可能。
着手金0円・相談料0円・調査料0円です。
こちらも詐欺問題に力を入れている司法書士事務所です。
費用の分割相談も可能。


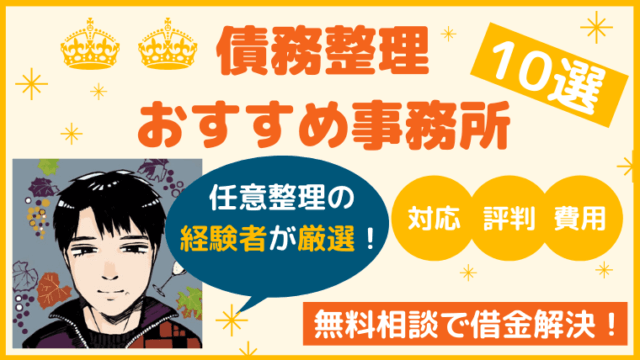

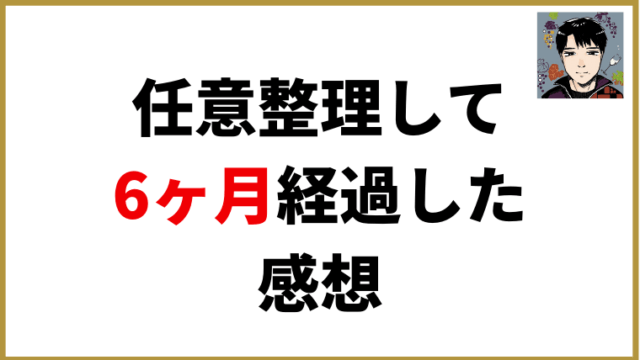

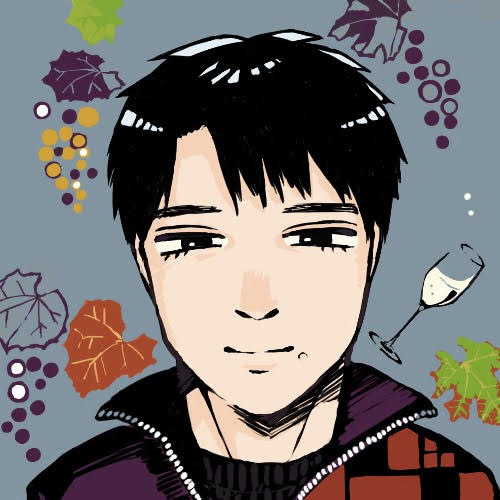
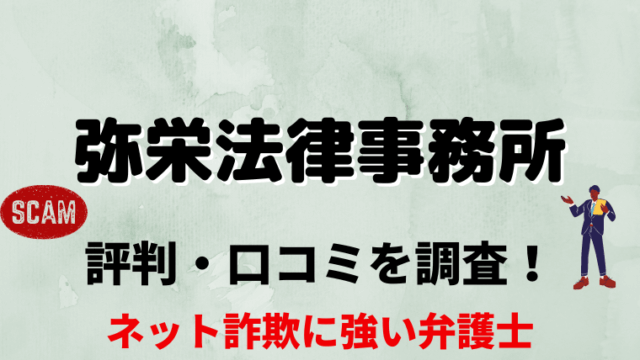
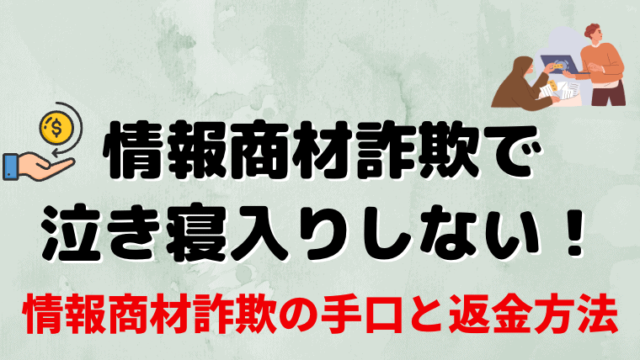
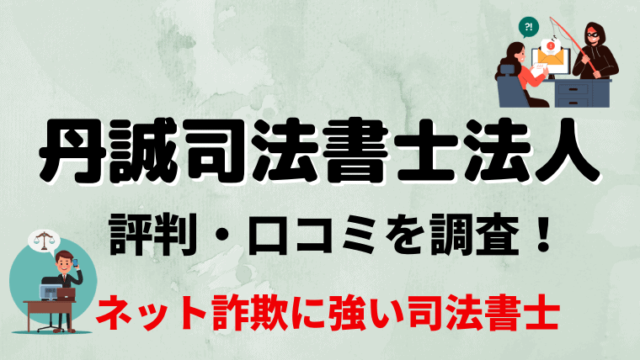
-min-1-640x360.png)