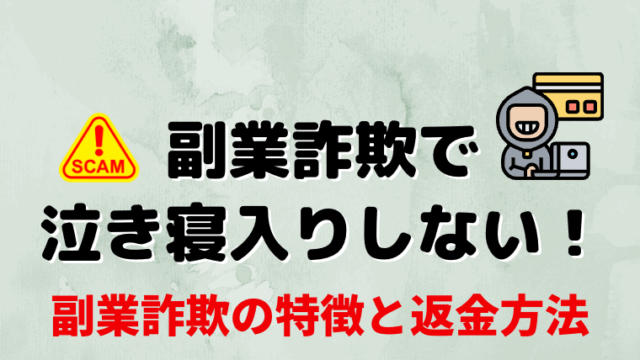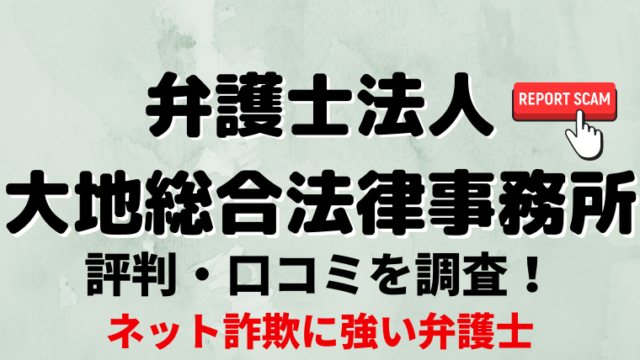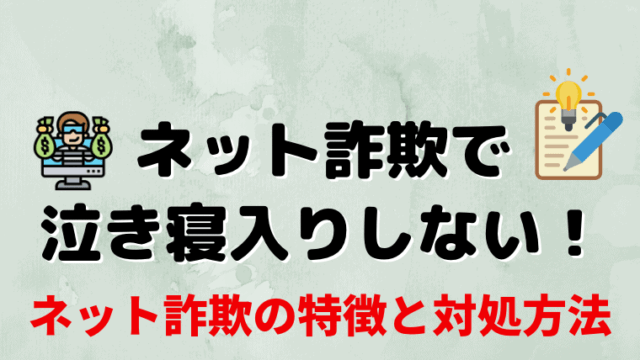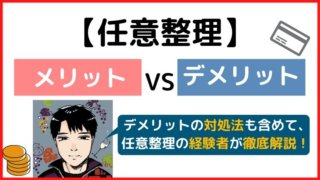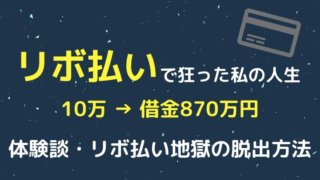近年、悪質な情報商材詐欺が増加しています。
「誰でも簡単に、大金を稼ぐことができる」のような謳い文句に釣られて、高額商品を購入してしまう被害が後を絶ちません。
そこで本記事では、情報商材の手口や返金方法、返金を成功させるコツを紹介します。
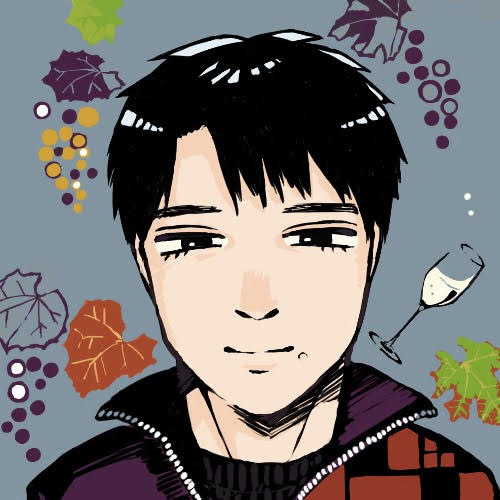
この記事を読んでわかること
- 情報商材詐欺の概要
- 情報商材詐欺の事例や手口
- 情報商材詐欺に遭ってしまったときの返金方法
- 情報商材詐欺の返金請求を成功させるコツ
\相談も調査も無料/情報商材詐欺の
相談はこちら>>
目次
情報商材詐欺とは?
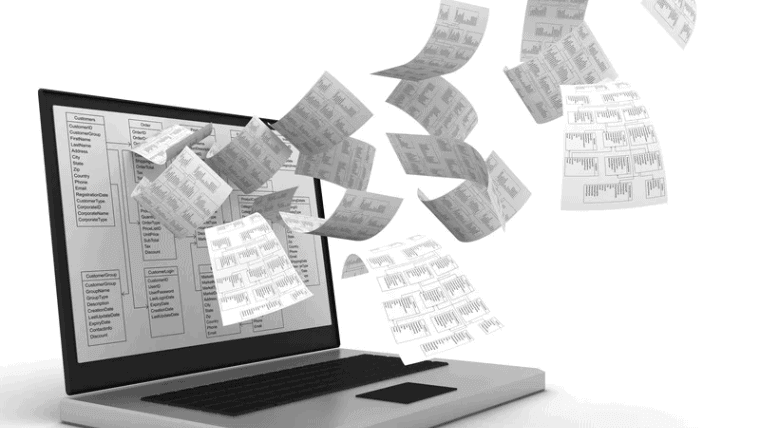
情報商材詐欺とは、高額の収入を得るための情報やノウハウを「法外な値段で販売する」詐欺です。
商品となる情報やノウハウをPDFや動画、オンラインセミナーなどの形にまとめて販売します。
よくある情報商材は、以下のようなものです。
- フリーランスの稼ぎ方
- 副業で稼ぐ方法
- 株式投資
- FX投資
- 仮想通貨投資
- パチンコ・競馬攻略法
- 恋愛ノウハウ(モテる方法・ナンパを成功させるコツ)
いずれも「楽して儲けたい」という人の欲望や弱みにつけ込んだものが多くみられます。
もちろん、情報商材のすべてが詐欺であるわけではありません。
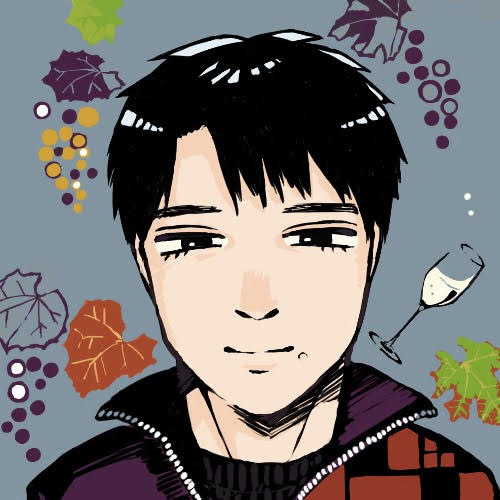
しかし、詐欺罪や特定商取引法違反の罪に該当するような、違法な情報商材詐欺が横行しているのも現実です。
情報商材詐欺の事例・手口
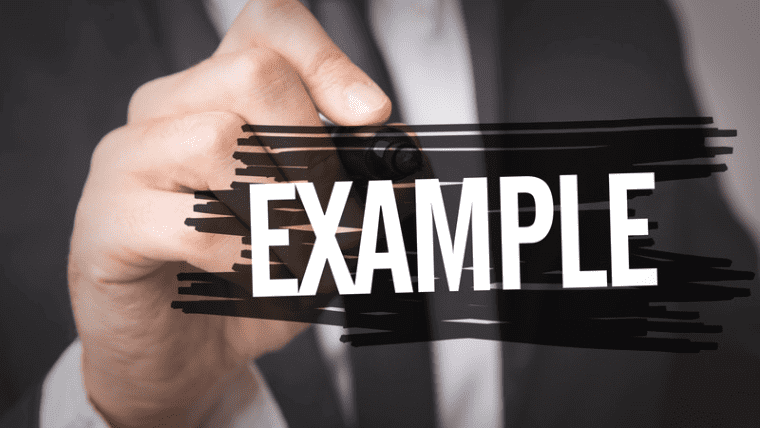
ここでは、情報商材詐欺の事例・手口をみていきましょう。
当てはまるものがすべて詐欺になるわけではありませんが、情報商材詐欺の多くは以下のような手口を活用しています。
【情報商材詐欺の事例・手口】
- ブログ・YouTube・LINEなどで誘導
- LP(ランディングページ)で勧誘
- メルマガやステップメールで囲い込み
- ASP・アフィリエイターを利用
- 無料オファーから高額商品へ誘導
ブログ・YouTube・LINEなどで誘導
ブログやYouTube、LINEなどから、販売ページへ誘導するパターンです。
一見、以下のように情報商材詐欺とわかりづらい例も増えています。
- 存在するアフィリエイターの運営サイトからリンクされている
- YouTube動画から公式LINEに登録させ、ステップ配信で勧誘する
- YouTube動画、SNS(Facebook・Twitter・Instagram)での広告で勧誘する
- 詐欺商材と知らずにインフルエンサーが販売する
また、アフィリエイトを介した販売も、情報商材詐欺を拡散させる要因になっています。
情報商材は、作成や仕入れなどに費用がかからないため、アフィリエイト報酬も高額なことが多いのです。
そのため、詐欺であることを認識しないまま、インフルエンサーやアフィリエイターによって商材の拡散が進んでしまうというわけです。
LP(ランディングページ)で勧誘
LP(ランディングページ)には、「情報商材」の魅力がふんだんに記載されています。
利用者の体験談などを掲載し、「いかに短期間でノウハウをマスターできたか」「いかに楽に稼ぐことができたか」を強調し、購買意欲をかきたてます。
そして「今だけ無料!」「今なら○%OFF!」という誘い文句で購入させる手口です。
メルマガやステップメールで囲い込み
メルマガやLINEに登録すると、「情報商材」の魅力をアピールするためのメールやメッセージが届くようになります。
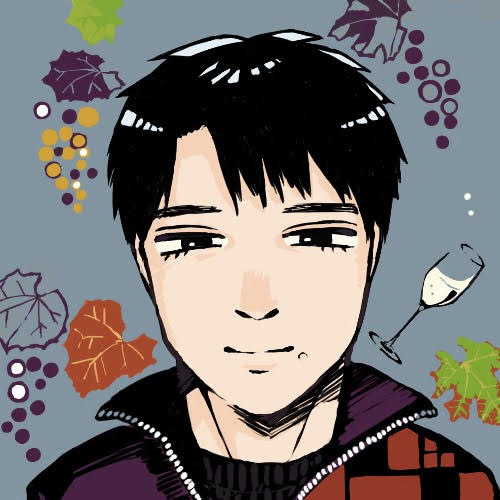
一定の間隔でメールを配信することによって、「情報商材」の購入が「お金儲けや目標達成に最適かつ最短の方法である」と洗脳する内容となっています。
そして、「商材が欲しい」と洗脳されたタイミングで「お得な金額で購入できる情報商材」の購入ページへ誘導→購入させるという手口です。
ASP・アフィリエイターを利用
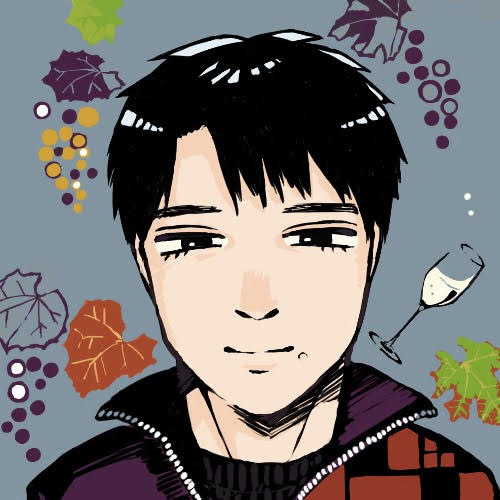
販売者が作成した詐欺商材を宣伝・紹介して手数料(アフィリエイト報酬)を得るアフィリエイターを利用する手口が、詐欺問題をより複雑化する要因となっています。
情報商材を販売するサイトをASPと言います。
ASP自体が詐欺を引き起こしている訳ではありませんが、審査基準が甘く中身のない情報商材でも、利益目的で売り出してしまうことが多いのも現状です。
無料オファーから高額商品へ誘導
無料セミナー、無料プレゼントなどで顧客の興味をひいたのち、高額商品の提案をして販売する手口です。
無料オファーは、正規のビジネスでも有用性が実証されているものの、宣伝や広告が派手になりやすく、情報商材詐欺の引き金となっていることも考えられます。
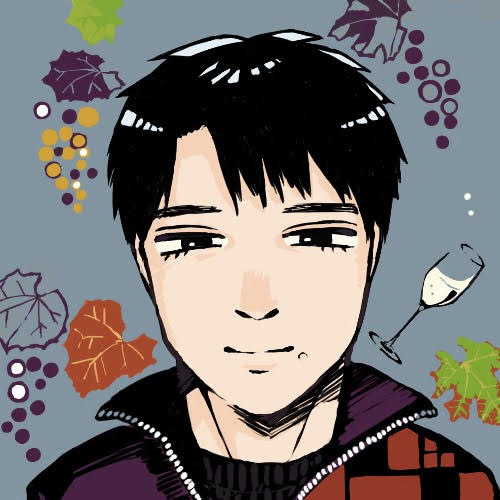
\相談も調査も無料/情報商材詐欺の
相談はこちら>>
情報商材詐欺を返金させる8つの対処法
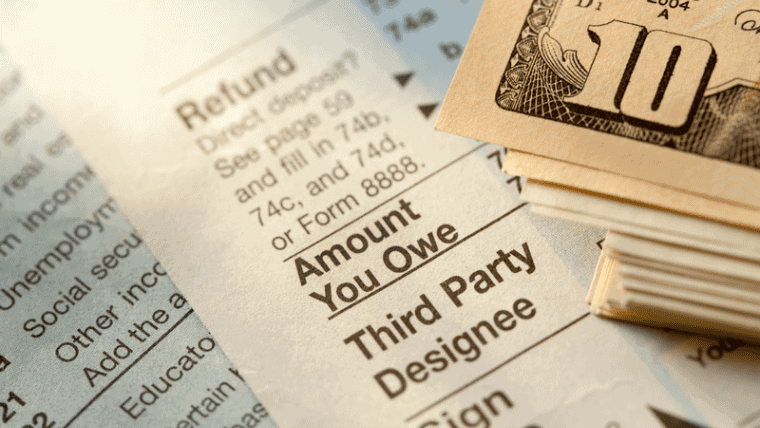
「購入した情報商材が詐欺かもしれない…」と不安をお持ちの方もいるでしょう。
情報商材詐欺の返金請求先として、主に次の4つが挙げられます。
- 情報商材の販売者
- ASP
- アフィリエイター
- クレジットカード会社・決済代行会社
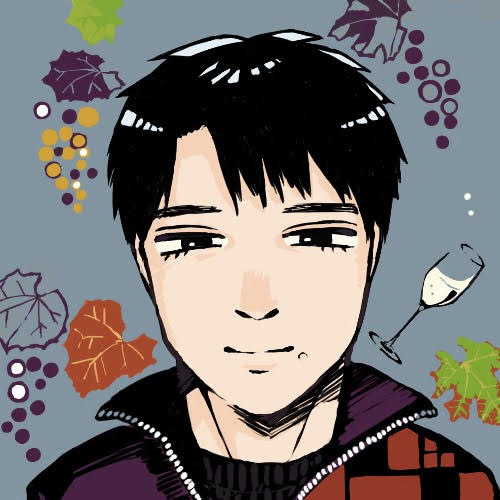
購入した情報商材が詐欺ではないかと気づいたら、迅速に返金請求方法を検討する必要があります。
ここでは、情報商材詐欺を返金させるための8つの方法を解説します。
販売者に返金保証を請求
まずは、購入した情報商材に返金保証の記載がないか確認しましょう。
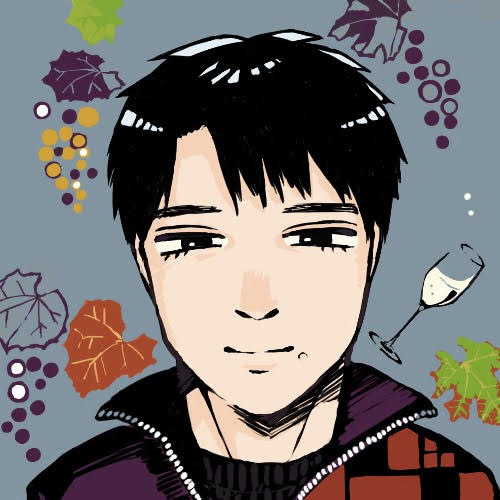
返金保証の一文が見つかれば、情報商材の販売者に対して返金保証に基づく返金請求をすることができます。
ただ、返金保証の記載があっても、実際は販売者が逃亡していたり、返金請求のために面倒な条件をつけたりと、なかなか返金に応じない詐欺業者もいます。
返金されない場合には、自分で解決することを考えるよりも、弁護士や司法書士に相談しましょう。
販売者に内容証明で返金請求
販売者が返金請求にすぐに応じない場合、内容証明で返金請求をおこないましょう。
法的な根拠をまとめ、応じないようであれば法的手段をとる旨を警告します。
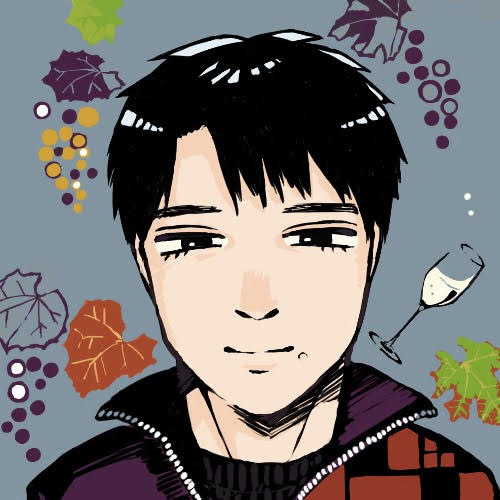
販売商材詐欺の勧誘や販売において、返金請求する法的な根拠には次の2つがあります。
- 詐欺による契約解除を理由とする返金請求(民法96条1項)
- 不法行為を理由とする損害賠償請求(民法709条)
そのほか、消費者を保護するための消費者契約法、特定商取引法、景品表示法といった法律に違反している可能性が高いです。
法的な根拠を確実にまとめて警告する必要があるため、弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。
決済代行業者に損害賠償請求
「販売者が返金請求に応じない」「すでに販売者の消息がわからない」といった場合には、決済代行業者に返済請求する方法を検討しましょう。
情報商材が詐欺である場合、決済代行業者も民法上の責任を負わなければなりません。
決済代行業者も、代金の一部を利益として受け取っているからです。
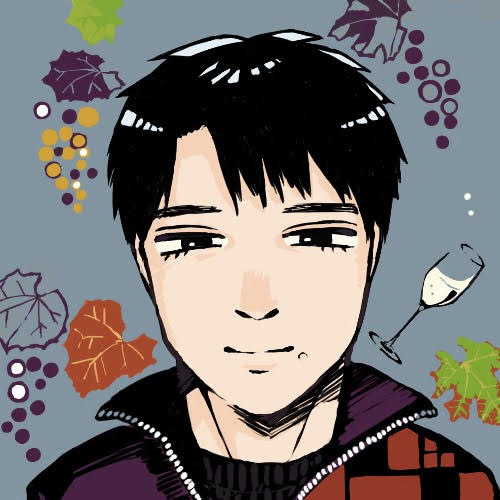
販売者への請求と同じく、法的な内容を記載し、内容証明で返金請求をします。
金融機関に口座凍結を要請
商材の代金を銀行口座に振り込んだ場合は、その金融機関に対して口座凍結を要請しましょう。
口座凍結の法的な根拠は、いわゆる「振り込め詐欺救済法」にあります。(正式名称:犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)
犯罪行為に利用された金融機関口座を凍結することで、被害拡大防止と被害回復を図ることが目的。
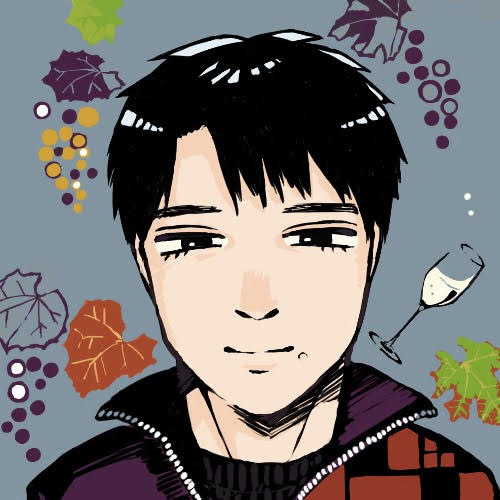
- どのようなサービスにどのように勧誘されたのか?
- どの口座にいくら振り込んだのか?
情報をまとめて、弁護士や司法書士に相談するとスムーズです。
クレジットカードの支払い停止の抗弁
クレジットカードの分割払い、割賦払い、リボ払いなどを利用して購入した場合は、クレジットカード会社に対して支払い停止の抗弁書を提出します。
支払い停止の抗弁とは?
「割賦販売法」に基づき、事業者の債務不履行や詐欺が発覚したとき、クレジットカード会社の支払いをストップし、支払い済みの代金を返金してもらう制度です。
しかし、抗弁を認めてもらうためには正当な理由が必要となるため、情報詐欺である証拠を集めなければなりません。
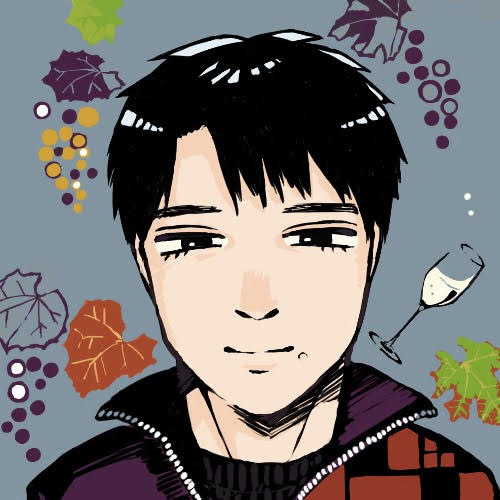
なお、一括払いで代金の支払いをおこなった場合は、支払い停止の抗弁が使えないため、次に説明するチャージバックの申請を検討しましょう。
チャージバック申請
クレジットカードの一括払いを利用した場合は、チャージバック申請をします。
チャージバックとは、クレジットカードの売上取り消しの処理のこと。
ただし、チャージバックがクレジットカード会社に認められるためには、正当な理由が必要です。
また、チャージバックはクレジットカード会社ごとに定めた期限があるため、早めの対応が必要になります。
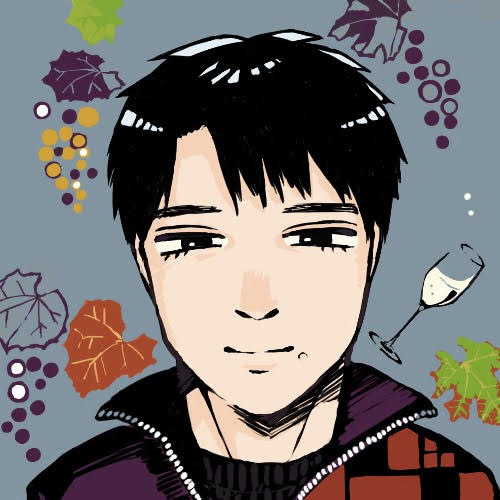
民事裁判による訴訟で返金請求
販売者に対して、内容証明による警告書で返金請求・損害賠償請求をおこなっても応じない場合は、民事裁判による訴訟で返金請求することを検討しましょう。
民事裁判の方法は、以下のとおりです。
- 裁判所に訴状を提出する
- 証拠を調べてもらい、情報商材販売者の民事責任を追求する
裁判に勝訴すれば、返金請求に応じてもらえるでしょう。
ただし、情報商材販売者に財産があることが前提となります。
刑事告訴・刑事告発
上記で解説した方法については、民事上の救済措置となります。
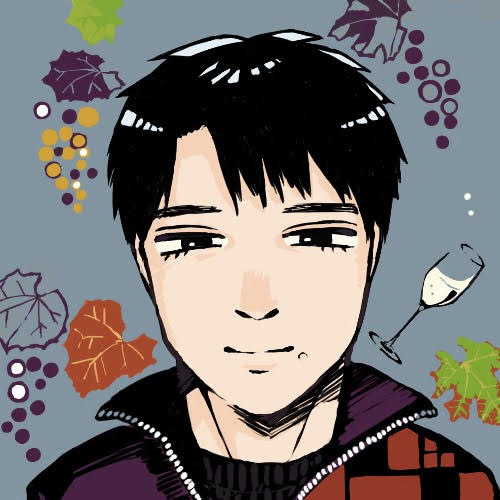
捜査機関(検察・警察)には強制的な捜査権があるため、民事上の方法で解決が難しかったとしても、返金を受けられる可能性があるでしょう。
ただし、刑事告訴を受理してもらうのはとても難しく、刑法に定められた「告訴状」の作成が求められます。
告訴状の作成には、刑事事件に関する知識・経験が豊富な弁護士のサポートが必要になります。
\相談も調査も無料/情報商材詐欺の
相談はこちら>>
情報商材詐欺はクーリングオフできる?
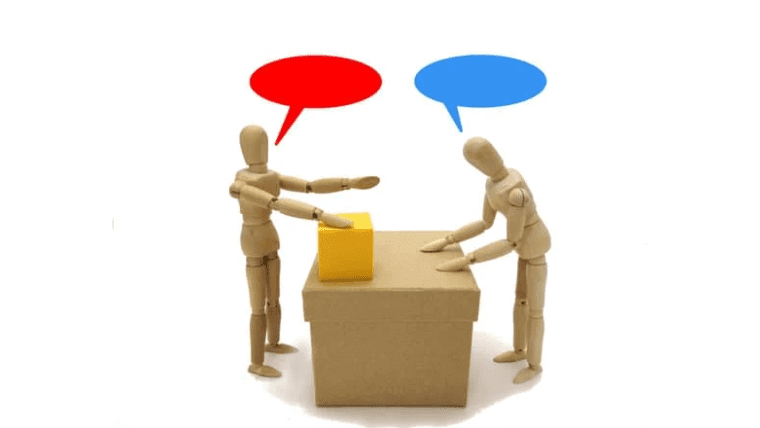
情報商材に限らず、ネット販売(通信販売)は原則としてクーリングオフができません。
ネット販売では、訪問販売や電話勧誘販売とは異なり、「自らの意思でサイトにアクセスし、商品を購入するか検討したうえで購入した」とみなされるため。
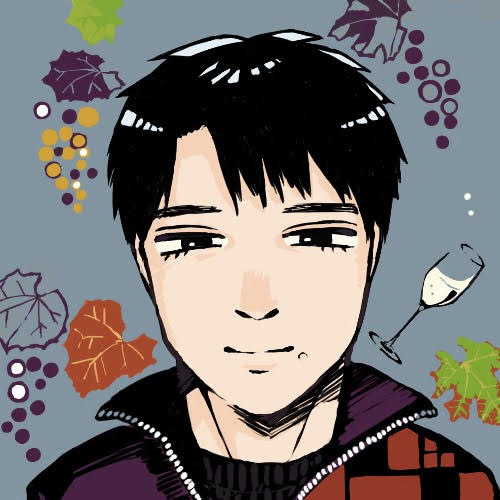
しかし、情報商材の販売サイトなどに「返品特約(返品の可否や返品条件)」が記載されていない場合は、クーリングオフが可能です。
クーリングオフは判断が難しいため、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
情報商材詐欺の返金請求を成功させる3つのコツ

ここでは、情報商材詐欺で返金請求を成功させる3つのコツを紹介します。
- 証拠を集める
- 特定商取引法に基づく表記を確認する
- 詐欺に強い弁護士・司法書士に相談する
証拠を集める
情報商材の返金請求を成功させるためにもっとも重要なのは、証拠を集めること。
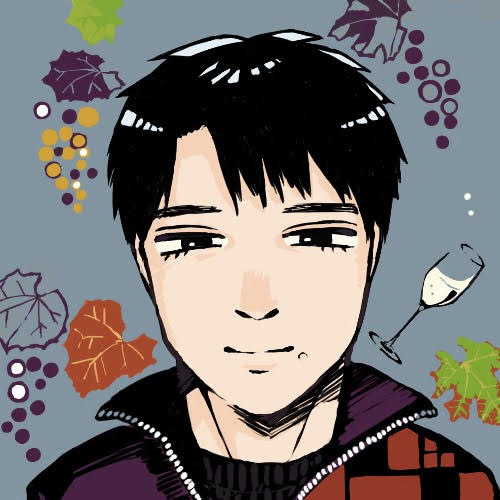
以下を参考に、関係するものはすべて記録して、証拠としてまとめておきましょう。
- 情報商材販売者の情報(会社名や住所、プロフィールなどわかるものはすべて)
- 販売サイトのURL・スクリーンショット
- メール履歴やその他のやりとり
- 代金の決済方法、銀行口座情報
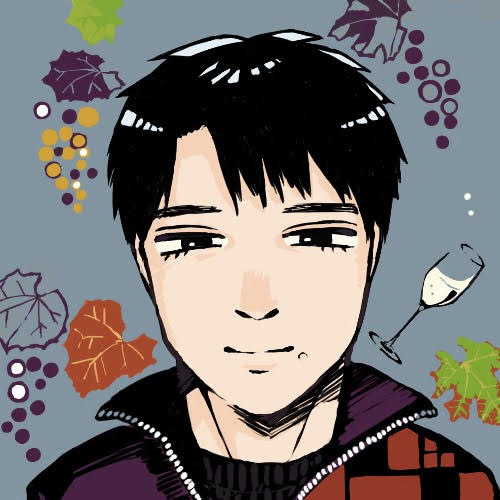
特定商取引法に基づく表記を確認する
販売サイトの「特定商取引法に基づく表記」を確認しておきましょう。
インターネットで商品を販売するときは、特定商取引法に基づいたページ作成が義務付けられています。
主に、次の項目を記載しなければなりません。
- 販売事業者の氏名(法人名)
- 販売に関する責任者名
- 所在地
- 商品代金以外にかかる料金の説明
- 引き渡し時期
- 支払い情報
- 電話番号
- メールアドレス
効果的な証拠として扱えるため、保存しておきましょう。
詐欺に強い弁護士・司法書士に相談する
返金請求を成功させるためには、詐欺に強い弁護士・司法書士に依頼することが重要です。
返金請求の手続きは、法的な知識が必要なので、自力で解決することは困難を極めます。
弁護士や司法書士に依頼すれば、早期解決が期待できるでしょう。
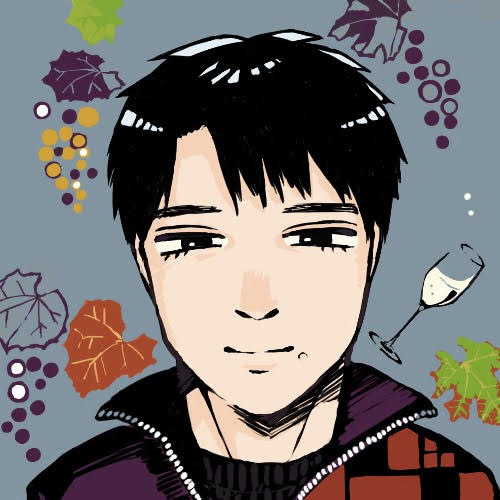
また、情報商材詐欺に遭ってしまったとき、警察に届ける方もいます。
しかし、警察は民事不介入なので、話は聞いてもらえるものの対応してもらうことができません。
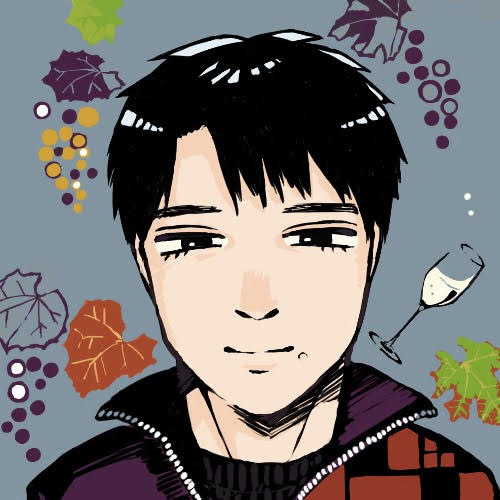
情報商材詐欺は一刻も早く対応する必要があるため、まずは弁護士・司法書士に相談しましょう。
\相談も調査も無料/情報商材詐欺に強い
専門家に相談する>>
情報商材詐欺と思ったら弁護士・司法書士に相談しよう

今回は、情報商材詐欺の手口や返金方法を紹介しました。
情報商材詐欺の手口はさまざまで、日々巧妙になっています。
また、相手が逃げ出したり、財産を使い込んでしまったりしては、返金できない可能性が高くなります。
万が一、詐欺被害に遭ってしまっても焦らずに、本記事を参考にして迅速に対応しましょう。
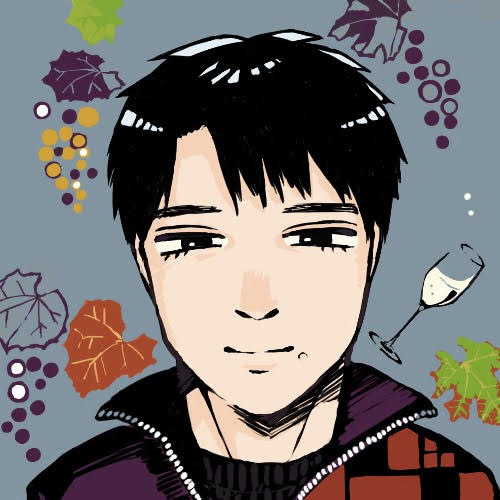
\相談も調査も無料/情報商材詐欺に強い
専門家に相談する>>


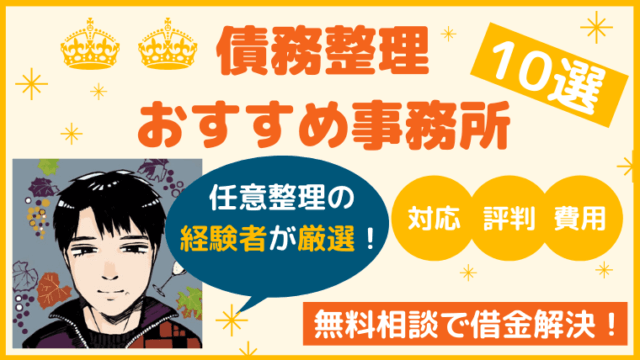

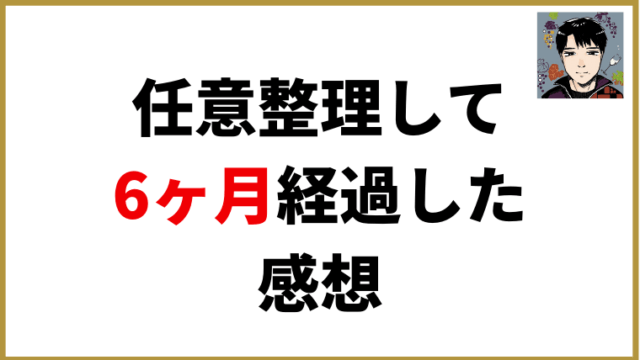
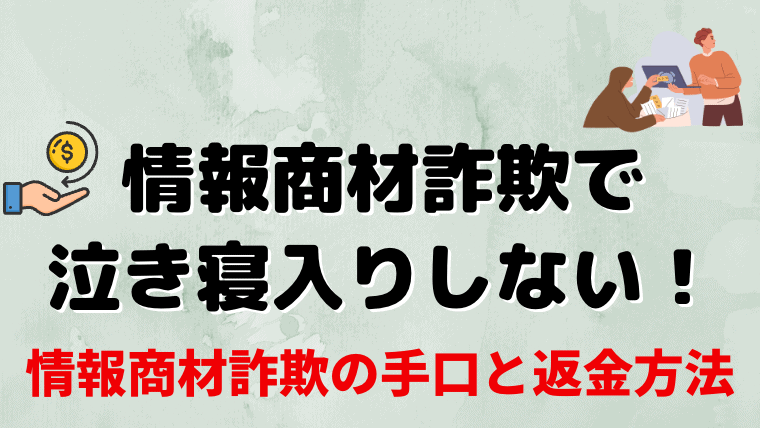
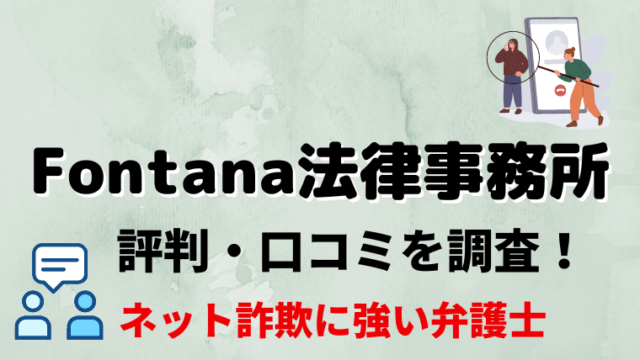
-min-1-640x360.png)